↓↓前編はこちら↓↓
脊柱管狭窄症に鍼灸は効果がある?
脊柱管狭窄症の痛みやしびれに対し、鍼灸治療が効果的だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、鍼灸治療は脊柱管狭窄症の症状緩和に役立つ可能性があると考えられています。
しかし、鍼灸単体で脊柱管狭窄症を根本的に治癒させることは難しいと考えられています。
あくまで、他の治療法と組み合わせて行うことで、より効果を発揮すると考えられています。
鍼灸が脊柱管狭窄症に作用するメカニズム
鍼灸治療は、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、脊柱管狭窄症に伴う痛みやしびれを軽減すると考えられています。
具体的には、以下のメカニズムが考えられます。
- 筋緊張緩和作用:鍼刺激がトリガーポイントと呼ばれる筋肉の硬結部位に作用することで、筋肉の緊張が緩和され、神経への圧迫が軽減されると考えられます。
- 血行促進作用:鍼やお灸の温熱刺激により血行が促進され、神経への栄養供給が改善し、老廃物の排出が促されると考えられます。
- 鎮痛作用:鍼刺激によってエンドルフィンなどの鎮痛物質が分泌され、痛みが軽減されると考えられます。
- 自律神経調整作用:鍼灸治療は自律神経のバランスを整える効果も期待でき、痛みやしびれなどの症状を改善する助けになると考えられます。
鍼灸治療のメリット
脊柱管狭窄症に対する鍼灸治療のメリットは、薬物療法のような副作用のリスクが低いこと、そして身体への負担が少ないことです。
また、痛みの緩和だけでなく、精神的なリラックス効果も期待できるため、脊柱管狭窄症の症状に悩む方にとって、QOL(生活の質)の向上に繋がる可能性があります。
| メリット | 説明 |
| 副作用が少ない | 薬物療法と比較して、副作用のリスクが低いと考えられています。 |
| 身体への負担が少ない | 手術療法のような身体への負担が少ないため、高齢の方でも安心して受けられます。 |
| リラックス効果 | 鍼灸治療は、心身のリラックスをもたらし、精神的なストレスを軽減する効果も期待できます。 |
| QOLの向上 | 痛みやしびれの軽減、リラックス効果などにより、日常生活の質の向上が期待できます。 |
しかし、鍼灸治療の効果には個人差があることを理解しておく必要があります。
また、症状によっては鍼灸治療が適さない場合もありますので、治療を受ける前に、専門家によく相談することが大切です。
他の治療法との併用も検討し、ご自身に合った治療法を選択するようにしてください。
脊柱管狭窄症で歩けない時の対処法
脊柱管狭窄症で歩けない、または歩行が困難な時は、日常生活にも大きな支障が出てしまいます。
少しでも症状を和らげ、快適に過ごすために、状況に応じた適切な対処法を知っておくことが大切です。
ここでは、脊柱管狭窄症で歩けない時の対処法を症状別に詳しく解説します。
症状別対処法
脊柱管狭窄症の症状は人それぞれ異なり、症状の重さによっても適切な対処法は変わってきます。
ご自身の症状に合った対処法を見つけることが重要です。
①間欠性跛行の対処法
間欠性跛行とは、しばらく歩くと足にしびれや痛みが出て歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになる症状です。
脊柱管狭窄症の代表的な症状の一つです。
間欠性跛行が出た時は、無理に歩き続けずに、すぐに休憩を取りましょう。
しばらく休むことで症状が和らぎ、再び歩けるようになります。
休憩する際は、椅子に座ったり、しゃがんだりするよりも、前かがみの姿勢になるのがおすすめです。
前かがみになることで脊柱管が広がり、神経への圧迫が軽減されるため、症状の緩和につながります。
| 症状 | 対処法 |
| 痛みやしびれで歩けない | 安全な場所に腰掛けて休憩する。前かがみの姿勢で休むのが効果的。 |
| 歩行が困難 | 杖や歩行器を使用する。 |
| 長時間の歩行が難しい | 休憩をこまめに入れる。目的地までの距離を分割して歩く。 |
②安静時のしびれや痛みの対処法
安静時にもしびれや痛みがある場合は、楽な姿勢を見つけることが重要です。
横向きに寝て膝を軽く曲げる、または仰向けに寝て膝の下にクッションを置くなど、自分に合った姿勢を探してみましょう。
温めることで血行が促進され、痛みが和らぐ場合もあります。
湯たんぽやホットタオルなどで患部を温めてみましょう。
ただし、炎症が強い場合は、冷やす方が効果的な場合もありますので、ご自身の状態に合わせて判断してください。
| 症状 | 対処法 |
| 安静時のしびれ | 横向きに寝て膝を軽く曲げる、または仰向けに寝て膝の下にクッションを置く。 |
| 安静時の痛み | 温める、または冷やす。自分に合った方法を見つける。 |
| 夜間の痛み | 寝る姿勢を工夫する。痛み止めを使用する場合は、医師に相談する。 |
③排尿・排便障害の対処法
脊柱管狭窄症が進行すると、まれに排尿・排便障害が起こる場合があります。
このような症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
自己判断で対処せずに、専門家の指示に従うことが重要です。
日常生活における注意点としては、水分をこまめに摂り、便秘にならないように食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るように心がけましょう。
日常生活での注意点
脊柱管狭窄症で歩けない時の対処法と合わせて、日常生活でも以下の点に注意することで、症状の悪化を防ぎ、快適に過ごすことができます。
- 適度な運動:ウォーキングや水中ウォーキングなど、腰に負担の少ない運動を続けることで、腰周りの筋肉を強化し、症状の改善に繋がります。ただし、痛みが出る場合は無理せず中止しましょう。
- 正しい姿勢を保つ:猫背や反り腰は脊柱管を狭くする原因となります。正しい姿勢を意識することで、症状の悪化を防ぐことができます。
- 体重管理:体重が増加すると腰への負担も大きくなり、症状が悪化する可能性があります。適正体重を維持するように心がけましょう。
- 長時間の同じ姿勢を避ける:デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチなどを行うようにしましょう。
これらの対処法を実践することで、脊柱管狭窄症の症状を和らげ、日常生活を快適に送ることができるでしょう。
ただし、症状が改善しない場合や悪化する場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしてください。
脊柱管狭窄症の予防法
脊柱管狭窄症は、加齢とともに進行しやすい疾患です。
しかし、日々の生活習慣を改善することで、発症や進行を遅らせることが期待できます。
適切な予防策を実践し、健康な脊柱を維持しましょう。
姿勢を正しく保つ
猫背や前かがみの姿勢は、背骨に負担をかけ、脊柱管狭窄症のリスクを高めます。
正しい姿勢を意識することで、背骨への負担を軽減し、脊柱管狭窄症の予防につながります。
デスクワークやスマートフォンの使用時には、こまめに休憩を取り、背筋を伸ばすように心がけましょう。
座る際は、骨盤を立てて背筋を伸ばし、あごを引いた姿勢を保つことが大切です。
また、立っている時も、お腹に力を入れて背筋を伸ばし、頭が体の中心にくるように意識しましょう。
適度な運動を行う
適度な運動は、背骨周りの筋肉を強化し、脊柱の安定性を高めます。
ウォーキングや水泳など、腰に負担の少ない運動を継続的に行うことが効果的です。
特に、水中ウォーキングは浮力によって腰への負担が軽減されるため、おすすめです。
ただし、激しい運動や急に無理な姿勢をとることは、逆に症状を悪化させる可能性があるので避けましょう。
運動前にストレッチを行うことも大切です。
自分の体力や体調に合わせて、無理のない範囲で運動を行いましょう。
バランスの良い食事を摂る
骨や筋肉の健康維持には、バランスの良い食事が不可欠です。
カルシウム、ビタミンD、タンパク質などを積極的に摂取することで、骨を丈夫にし、脊柱管狭窄症の予防に役立ちます。
カルシウムは牛乳や乳製品、小魚、緑黄色野菜などに多く含まれています。
ビタミンDは鮭やさんまなどの魚類、きのこ類、卵などに多く含まれています。
タンパク質は肉、魚、卵、大豆製品などに多く含まれています。
これらの栄養素をバランス良く摂取することで、骨や筋肉の健康を維持し、脊柱管狭窄症の予防に繋げましょう。
体重管理を心がける
過剰な体重は、脊柱に大きな負担をかけ、脊柱管狭窄症のリスクを高めます。
適正体重を維持することで、脊柱への負担を軽減し、発症や進行を予防することができます。
バランスの良い食事と適度な運動を組み合わせ、健康的な体重管理を心がけましょう。
急激なダイエットは体に負担をかけるため、避けましょう。
ゆっくりと時間をかけて、無理のない範囲で体重を落とすことが大切です。
禁煙する
喫煙は、血行不良を引き起こし、骨や椎間板への栄養供給を阻害します。
禁煙することで、脊柱の健康を維持し、脊柱管狭窄症のリスクを低減することができます。
| 予防策 | 具体的な方法 |
| 正しい姿勢 | デスクワーク時はこまめな休憩、正しい座り方、立位姿勢の意識 |
| 適度な運動 | ウォーキング、水泳、水中ウォーキング、ストレッチ |
| バランスの良い食事 | カルシウム、ビタミンD、タンパク質の摂取 |
| 体重管理 | 適正体重の維持、バランスの良い食事と適度な運動 |
| 禁煙 | 禁煙による血行改善 |
これらの予防策を日々の生活に取り入れることで、脊柱管狭窄症の発症や進行を遅らせることが期待できます。
ご自身の体に合った方法で、無理なく継続していくことが大切です。
まとめ
脊柱管狭窄症で歩けないほどの症状に悩まされている方は、不安を抱えていることでしょう。
この記事では、脊柱管狭窄症の症状や原因、一般的な治療法、そして鍼灸の効果について解説しました。
加齢などが原因で脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで、間欠性跛行やしびれ、痛みが生じます。
症状が悪化すると歩行困難になることもあります。
一般的な治療法には、薬物療法、理学療法、装具療法、手術療法などがあります。
鍼灸治療は、血行促進や筋肉の緊張緩和による疼痛軽減効果が期待できるため、保存療法の一つとして検討されることがあります。
しかし、鍼灸が脊柱管狭窄症の根本的な原因を解決するものではないこと、症状の改善には個人差があることを理解しておく必要があります。
つらい症状でお困りの際は、まずは医療機関に相談し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
この記事が、脊柱管狭窄症についての理解を深め、治療法を選択する際の一助となれば幸いです。
お悩みの方は当院へご相談ください。
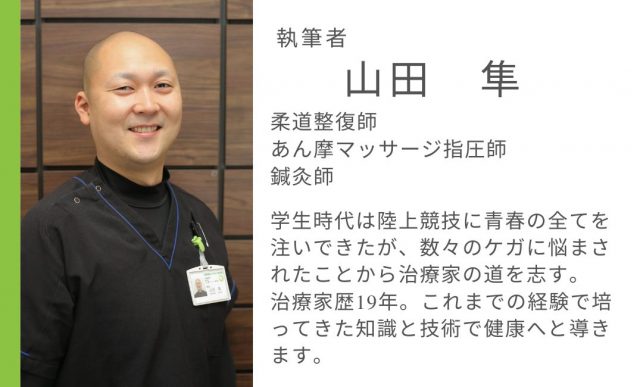

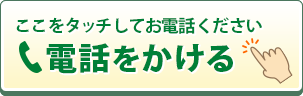
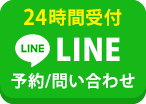
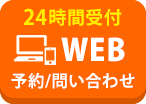





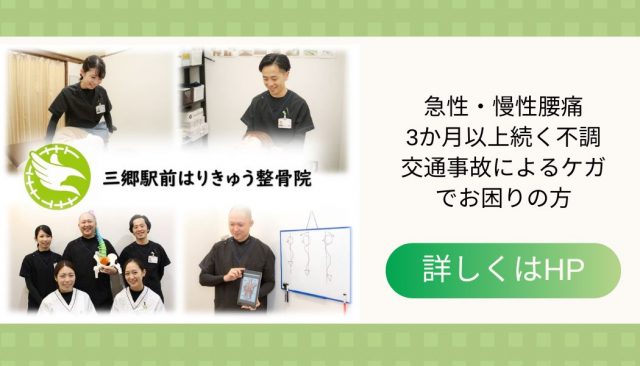
お電話ありがとうございます、
三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。