坐骨神経痛とは?その原因と症状
坐骨神経痛とは、腰から足にかけて伸びている坐骨神経が圧迫されたり刺激されたりすることで、腰、お尻、太もも、ふくらはぎ、足先に痛みやしびれなどの症状が現れる状態のことです。
痛みは鋭い痛みや鈍い痛み、電気が走るような痛みなど様々で、人によって感じ方も異なります。
また、しびれや感覚の鈍麻、筋力低下などを伴う場合もあります。
坐骨神経痛自体は病名ではなく、様々な原因によって引き起こされる症状の総称であることを理解しておくことが重要です。
坐骨神経痛の主な原因
坐骨神経痛の主な原因は、腰椎椎間板ヘルニアです。
椎間板の一部が飛び出し、坐骨神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こします。
その他にも、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群、脊椎すべり症、骨盤の歪み、妊娠など、様々な原因が考えられます。
| 原因 | 説明 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 椎間板の一部が飛び出し、神経を圧迫する |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 神経の通り道が狭くなり、神経を圧迫する |
| 梨状筋症候群 | お尻の筋肉である梨状筋が坐骨神経を圧迫する |
| 脊椎すべり症 | 腰椎の一部が前方にずれることで神経を圧迫する |
| 骨盤の歪み | 骨盤の歪みによって坐骨神経が圧迫される |
| 妊娠 | 大きくなった子宮が坐骨神経を圧迫する |
坐骨神経痛の代表的な症状
坐骨神経痛の症状は、腰から足にかけての痛みやしびれが代表的です。
その痛みやしびれの程度や範囲は、原因や個々の状態によって大きく異なります。
鋭い痛みを感じることもあれば、鈍い痛みや電気が走るような痛みを感じることもあります。
また、お尻や太もも、ふくらはぎ、足先などに痛みやしびれが広がる場合もあります。
さらに、足の冷えや感覚の鈍麻、筋力低下といった症状が現れる場合もあります。
症状が軽い場合は、安静にしていれば自然と治まることもありますが、症状が重い場合や長引く場合は、適切な対処が必要となります。
坐骨神経痛の症状は多岐にわたるため、自己判断せずに専門家に相談することが大切です。
坐骨神経痛に効果的なツボの種類と効果
坐骨神経痛の痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。
辛い症状を少しでも和らげるために、効果的なツボ押しを試してみましょう。
ここでは、坐骨神経痛に効果的なツボの種類とそれぞれの効果について詳しく解説します。
腰痛や臀部の痛みを和らげるツボ
腰やお尻の痛みは、坐骨神経痛の初期症状としてよく見られます。
これらの痛みを和らげるツボを効果的に刺激することで、症状の悪化を防ぎ、快適な生活を取り戻す助けとなります。
①環跳(かんちょう)
環跳は、お尻の外側、腰骨の上端と大転子(太ももの付け根の出っ張り)を結んだ線の中央よりやや後方に位置するツボです。
腰やお尻の痛み、坐骨神経痛による足のしびれやだるさを和らげる効果があるとされています。
仰向けに寝て膝を曲げた状態で、親指または人差し指でゆっくりと押してください。
②秩辺(ちっぺん)
秩辺は、お尻の中央、仙骨のすぐ下にあるツボです。
腰痛、臀部の痛み、坐骨神経痛による下肢の痛みやしびれに効果があるとされています。
うつ伏せになり、両膝を軽く曲げた状態で、親指でゆっくりと押してください。
脚の痺れに効くツボ
坐骨神経痛の症状が進行すると、脚にしびれが現れることがあります。
これらのしびれは、日常生活での歩行や動作を困難にする場合もあります。
以下のツボを刺激することで、しびれの緩和を目指しましょう。
①承扶(しょうふ)
承扶は、太ももの裏側、お尻の真ん中にある横線の中央に位置するツボです。
坐骨神経痛による太ももの裏側の痛みやしびれ、足の冷えなどに効果があるとされています。
椅子に座るか、うつ伏せに寝た状態で、親指でゆっくりと押してください。
②殷門(いんもん)
殷門は、太ももの裏側、膝裏の中央から指4本分上がったところに位置するツボです。
坐骨神経痛による太ももの痛みやしびれ、足のむくみなどに効果があるとされています。
椅子に座るか、うつ伏せに寝た状態で、親指でゆっくりと押してください。
坐骨神経痛全体の症状緩和に効果的なツボ
坐骨神経痛の症状は、腰や臀部だけでなく、脚全体に広がることもあります。
以下のツボは、坐骨神経痛全体の症状緩和に効果があるとされています。
①委中(いちゅう)
委中は、膝の裏側、中央のくぼみに位置するツボです。
坐骨神経痛による腰痛、膝の痛み、足のしびれなどに効果があるとされています。
膝を軽く曲げた状態で、親指でゆっくりと押してください。
②崑崙(こんろん)
崑崙は、外くるぶしとアキレス腱の間にあるツボです。
坐骨神経痛による腰痛、足の痛みやしびれ、かかとの痛みなどに効果があるとされています。
椅子に座るか、あぐらを組んだ状態で、親指でゆっくりと押してください。
| ツボ | 位置 | 効果 |
| 環跳 | 腰骨の上端と大転子を結んだ線の中央よりやや後方 | 腰やお尻の痛み、足のしびれやだるさ |
| 秩辺 | お尻の中央、仙骨のすぐ下 | 腰痛、臀部の痛み、下肢の痛みやしびれ |
| 承扶 | 太ももの裏側、お尻の真ん中にある横線の中央 | 太ももの裏側の痛みやしびれ、足の冷え |
| 殷門 | 太ももの裏側、膝裏の中央から指4本分上がったところ | 太ももの痛みやしびれ、足のむくみ |
| 委中 | 膝の裏側、中央のくぼみ | 腰痛、膝の痛み、足のしびれ |
| 崑崙 | 外くるぶしとアキレス腱の間 | 腰痛、足の痛みやしびれ、かかとの痛み |
ツボ押しは、坐骨神経痛の症状緩和に役立つ方法の一つですが、痛みが強い場合や症状が改善しない場合は、専門家にご相談ください。
ご自身の症状に合った適切な治療を受けることが大切です。
鍼灸による坐骨神経痛の根本改善
坐骨神経痛でお悩みの方の中には、痛みや痺れがなかなか改善せず、根本的な解決策を探している方も多いのではないでしょうか。
坐骨神経痛の治療法として、鍼灸が注目されています。
鍼灸は、身体に鍼を刺したり、もぐさを燃やして温熱刺激を与えたりすることで、痛みや痺れなどの症状を緩和するだけでなく、身体の機能を回復させる効果も期待できます。
鍼灸が坐骨神経痛に効果的な理由
鍼灸が坐骨神経痛に効果的な理由は、主に以下の3つのメカニズムによるものです。
・血行促進作用:鍼灸刺激は、患部の血行を促進します。血行が良くなることで、筋肉や神経への酸素供給が向上し、疲労物質や老廃物が排出されやすくなります。結果として、筋肉の緊張が緩和され、痛みや痺れが軽減されます。
・鎮痛作用:鍼灸刺激は、脳内でエンドルフィンなどの鎮痛物質の分泌を促進すると言われています。これらの物質は、モルヒネの数倍もの鎮痛効果を持つとされ、自然な形で痛みを和らげる効果が期待できます。
・神経機能の調整作用:坐骨神経痛は、神経が圧迫されたり炎症を起こしたりすることで引き起こされます。鍼灸刺激は、自律神経系に作用し、神経の働きを調整することで、神経の炎症を抑えたり、圧迫を軽減したりする効果が期待できます。
鍼灸治療の種類と期待できる効果
鍼灸治療には様々な種類があり、それぞれ異なる効果が期待できます。
坐骨神経痛に用いられる主な鍼灸治療と、その期待できる効果を以下にまとめました。
| 治療の種類 | 期待できる効果 |
| 鍼治療 | 筋肉の緊張緩和、血行促進、鎮痛効果 |
| 灸治療 | 温熱効果による血行促進、鎮痛効果、冷えの改善 |
| 電気鍼 | 鍼に微弱な電流を流すことで、より強い鎮痛効果と筋肉の弛緩効果 |
| 灸頭鍼 | 間歇的に温熱刺激を与えることで、持続的な血行促進効果と鎮痛効果 |
鍼灸治療は、身体への負担が少ない治療法であり、副作用も比較的少ないとされています。
また、鍼灸治療の効果には個人差があります。
数回の施術で効果を実感できる場合もあれば、継続的な治療が必要な場合もあります。
治療を受ける際は、鍼灸師とよく相談し、治療計画を立てていくことが重要です。
坐骨神経痛のセルフケア方法
坐骨神経痛の症状緩和には、専門家による施術と並行して、自宅で行えるセルフケアも重要です。
セルフケアを継続的に行うことで、症状の改善を促し、再発予防にも繋がります。
ここでは、ツボ押しマッサージ、ストレッチ、日常生活での注意点について詳しく解説します。
ツボ押しマッサージ
ツボ押しマッサージは、指でツボを刺激することで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。
痛みや痺れを感じている部分だけでなく、関連するツボを刺激することで、より効果的に症状を緩和できる場合があります。
以下のツボを、息を吐きながらゆっくりと3~5秒ほど押してみてください。
1日に数回行うのがおすすめです。
| ツボの名前 | 位置 | 効果 |
| 環跳(かんちょう) | お尻の外側、腰骨と太ももの骨を結んだ線の中央よりやや外側 | 腰痛、臀部の痛みを和らげる |
| 秩辺(ちっぺん) | お尻の真ん中あたり、仙骨の上端から左右に指幅3本分外側 | 腰痛、臀部の痛みを和らげる |
| 承扶(しょうふ) | 太ももの裏側、お尻の真ん中と膝裏の中間 | 脚の痺れ、痛みを和らげる |
| 殷門(いんもん) | 太ももの裏側、膝裏と承扶の中間 | 脚の痺れ、痛みを和らげる |
| 委中(いちゅう) | 膝裏の中央 | 坐骨神経痛全体の症状緩和 |
| 崑崙(こんろん) | 外くるぶしとアキレス腱の間 | 坐骨神経痛全体の症状緩和 |
ツボ押しは、強い痛みを感じるほど強く押す必要はありません。
気持ち良いと感じる程度の強さで刺激するのがポイントです。
また、妊娠中の方や持病のある方は、事前に医師に相談してから行うようにしてください。
ストレッチ
ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進することで、坐骨神経痛の症状緩和に繋がります。
無理のない範囲で、毎日続けることが大切です。
痛みを感じる場合は、すぐに中止してください。
①太もも裏のストレッチ
仰向けに寝て、片方の足を両手で抱え、胸の方に引き寄せます。
この姿勢を20~30秒ほど維持します。反対側も同様に行います。
②お尻のストレッチ
仰向けに寝て、片方の足を曲げ、反対側の太ももに乗せます。
そのまま上体を倒し、20~30秒ほど維持します。
反対側も同様に行います。
③股関節のストレッチ
椅子に座り、片方の足を反対側の太ももに乗せます。
そのまま上体を倒し、20~30秒ほど維持します。反対側も同様に行います。
日常生活での注意点
日常生活における姿勢や動作は、坐骨神経痛の症状に大きく影響します。
正しい姿勢を意識し、体に負担をかけない動作を心がけることで、症状の悪化や再発を予防することができます。
- 同じ姿勢を長時間続けない:デスクワークや長時間の運転など、同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチや体操を行うようにしましょう。
- 重いものを持ち上げるときは、膝を曲げて持ち上げる:腰に負担がかからないように、膝を曲げて持ち上げるようにしましょう。また、重いものを持ち上げる際は、できる限り複数人で協力するようにしてください。
- 適切な寝具を選ぶ:硬すぎるマットレスや柔らかすぎるマットレスは、腰に負担をかける可能性があります。自分に合った硬さのマットレスを選び、適切な睡眠姿勢を保つようにしましょう。
- 冷えに注意する:体が冷えると、血行が悪くなり、筋肉が緊張しやすくなります。特に冬場は、温かい服装を心がけ、体を冷やさないように注意しましょう。
これらのセルフケアは、坐骨神経痛の症状緩和に役立ちますが、あくまで補助的な役割です。
症状が改善しない場合や悪化する場合は、自己判断せずに、専門家に相談するようにしてください。
まとめ
坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が圧迫されたり刺激されることで、臀部や脚に痛みやしびれが生じる症状です。
この記事では、坐骨神経痛の原因と症状、そして効果的なツボの種類とそれぞれの効果について解説しました。
環跳や秩辺といった腰臀部の痛みを和らげるツボ、承扶や殷門といった脚のしびれに効くツボ、委中や崑崙といった坐骨神経痛全体の症状緩和に効果的なツボをご紹介しました。
これらのツボ押しマッサージやストレッチは、自宅でできる手軽なセルフケアとして役立ちます。
さらに、鍼灸治療は、ツボへの刺激を通じて血行を促進し、筋肉の緊張を緩和することで、坐骨神経痛の根本改善を目指せる方法の一つです。
日常生活では、正しい姿勢を保つ、重いものを持ち上げないなど、坐骨神経への負担を軽減するよう心がけることが大切です。
ご紹介したセルフケアや日常生活での注意点を実践することで、坐骨神経痛の症状緩和に繋がる可能性があります。
何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
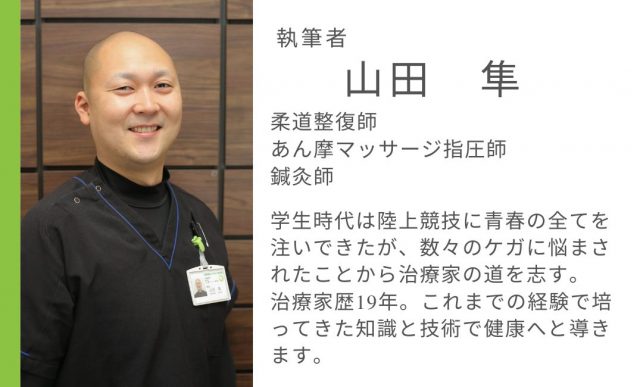

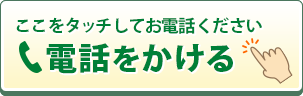
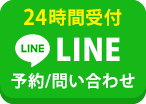
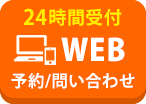





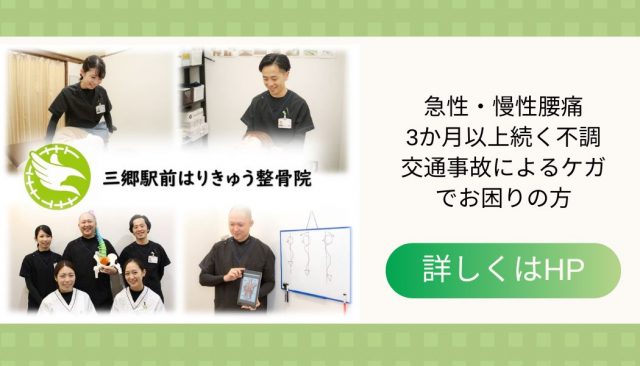
お電話ありがとうございます、
三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。