足の裏の痺れってどんな症状?
足の裏の痺れは、様々な形で現れます。
ピリピリとした軽いものから、ジンジンとした強いもの、また、感覚が鈍くなる、麻痺のような状態になるなど、その感じ方は人それぞれです。
さらに、常に痺れている場合や、歩行時など特定の動作をした時にだけ痺れが出る場合、朝起きた時だけ痺れている場合など、症状が現れるタイミングも様々です。
痺れと同時に、冷感や灼熱感、痛みを伴う場合もあります。
また、足の裏だけでなく、足先やふくらはぎ、太ももなど、他の部位にも痺れが広がっているケースも見られます。
これらの症状は、原因となる疾患によって異なるため、自身の症状を詳しく把握することが重要です。
足の裏の痺れの症状
足の裏の痺れは、その症状の現れ方によって、いくつかの種類に分けられます。
| 症状の種類 | 具体的な症状 |
| 感覚鈍麻 | 触られた感覚が鈍い、温度感覚が分かりにくいなど、感覚がにぶる状態です。 |
| 異常感覚 | 実際には何も触れていないのに、何かが這っているような感覚や、チクチク、ビリビリとした痛みを伴う痺れです。 |
| しびれ | 感覚が麻痺したような状態になり、何も感じなくなることもあります。 |
| 違和感 | 足の裏に何か違和感がある、なんとなく気持ち悪い、締め付けられるような感覚など、漠然とした不快感を覚えることもあります。 |
これらの症状は、単独で現れることもあれば、いくつかが組み合わさって現れることもあります。
また、症状の強さも、軽度なものから日常生活に支障をきたすほどの重度なものまで様々です。
足の裏の痺れを放置するとどうなる?
足の裏の痺れを放置すると、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
初期段階では軽い痺れであっても、根本的な原因に対処せずに放置することで、症状が悪化し、歩行困難になるケースもあります。
また、痺れだけでなく、痛みやしびれの範囲が広がる、筋力低下が起こるといった症状が現れることもあります。
さらに、足の裏の痺れの原因が重大な疾患である場合、早期発見・早期治療を行わないことで、病状が進行し、日常生活に大きな支障をきたす可能性も考えられます。
例えば、脊髄の圧迫が原因で痺れが出ている場合、放置すると神経がさらに圧迫され、排尿・排便障害などの重篤な症状につながる可能性も否定できません。
そのため、足の裏の痺れを感じたら、たとえ軽度であっても、放置せずに早めに専門家へ相談することが大切です。
自己判断で対処しようとせず、適切な検査と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、健康な状態を維持することができます。
足の裏の痺れの原因は?ヘルニアの可能性は?
足の裏の痺れは、様々な原因で起こり得ます。
その中でも、ヘルニアが原因となっているケースは少なくありません。
ここでは、ヘルニアによる足の裏の痺れについて詳しく解説し、ヘルニア以外の原因についてもご紹介します。
ヘルニアによる足の裏の痺れ
ヘルニアとは、組織の一部が本来あるべき場所から飛び出してしまう状態のことを指します。
脊椎に発生するヘルニアは、神経を圧迫し、痺れや痛みを引き起こすことがあります。
足の裏の痺れにつながるヘルニアには、主に以下の2種類があります。
①腰椎椎間板ヘルニア
腰椎椎間板ヘルニアは、腰椎にある椎間板の一部が飛び出し、神経を圧迫することで起こります。
この飛び出した部分が坐骨神経を圧迫すると、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足の裏にかけて痺れや痛み、違和感などが現れることがあります。
症状の程度は、飛び出した椎間板の大きさや神経への圧迫の程度によって異なります。
咳やくしゃみをした際に痛みが強くなることもあります。
②脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症は、加齢などが原因で脊柱管(神経の通り道)が狭くなり、神経が圧迫されることで起こります。
腰部で神経が圧迫されると、足の裏の痺れだけでなく、間欠性跛行(しばらく歩くと足に痛みや痺れが出て歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになる症状)が現れることもあります。
ヘルニア以外の足の裏の痺れの原因
足の裏の痺れは、ヘルニア以外にも様々な原因で起こり得ます。
代表的なものとしては以下のものがあります。
| 疾患名 | 症状 | 原因 |
| 坐骨神経痛 | お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足の裏にかけての痛みや痺れ | 腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などによって坐骨神経が圧迫されることで起こる |
| 末梢神経障害 | 手足の痺れや痛み、感覚の鈍化など | 糖尿病、アルコール多飲、ビタミン不足など様々な原因で末梢神経が障害されることで起こる |
| 糖尿病 | 高血糖による様々な症状(口渇、多飲、多尿、体重減少など)に加え、末梢神経障害による手足の痺れなども起こり得る | インスリンの作用不足によって慢性的に高血糖状態となることで起こる |
| 足根管症候群 | 足の裏や踵、つま先の痺れや痛み、灼熱感 | 足首の内側にある足根管というトンネルの中で神経が圧迫されることで起こる |
| モートン病 | 足の裏、特に第3指と第4指の間の付け根に痛みや痺れ、灼熱感など | 足指につながる神経が圧迫されることで起こる |
| 血行不良 | 足の裏の冷え、痺れ、むくみなど | 動脈硬化や冷え性などによって足への血流が悪くなることで起こる |
これらの疾患以外にも、長時間の立ち仕事や、窮屈な靴を履くことなども、足の裏の痺れの原因となることがあります。
痺れが長引く場合や、日常生活に支障をきたす場合は、自己判断せずに専門家へ相談することが大切です。
足の裏の痺れと鍼灸治療
足の裏の痺れに対し、鍼灸治療は効果が期待できる選択肢の一つです。
古来より伝わる東洋医学に基づいた鍼灸治療は、身体全体のバランスを整え、自然治癒力を高めることで、痺れの根本原因にアプローチします。
鍼灸治療が足の裏の痺れに効果的な理由
鍼灸治療は、ツボを刺激することで血行を促進し、筋肉の緊張を緩和します。
また、神経系の働きを調整することで、痛みや痺れといった症状を和らげる効果も期待できます。
特に、ヘルニアによる神経圧迫が原因で起こる足の裏の痺れに対しては、鍼灸治療によって血行が改善され、神経への圧迫が軽減されることで、症状の緩和につながることがあります。
西洋医学的な治療とは異なり、鍼灸治療は身体への負担が少ないというメリットもあります。
薬物療法のような副作用の心配も少なく、体質改善を目的とした治療としても有効です。
| 鍼灸治療の効果 | メカニズム |
| 血行促進 | ツボ刺激による血管拡張作用 |
| 筋肉の緊張緩和 | 筋肉への直接的な刺激と血行促進効果 |
| 神経機能の調整 | 自律神経系への作用 |
| 自然治癒力の向上 | 身体全体のバランス調整 |
鍼灸治療の流れ
鍼灸治療を受ける際の流れは、一般的に以下のようになります。
①問診
施術者はまず、現在の症状や既往歴、生活習慣などについて詳しく問診を行います。
足の裏の痺れがいつから始まったのか、どのような時に症状が悪化するのかなど、些細なことでも伝えることが大切です。
正確な情報を伝えることで、より適切な治療を受けることができます。
②触診
問診後、施術者は実際に身体に触れて、筋肉の状態や痛みの有無などを確認します。
触診によって、痺れの原因となっている筋肉や神経の状態を把握します。
③施術
触診に基づき、施術者は適切なツボを選び、鍼やお灸で刺激を与えます。
鍼は髪の毛ほどの細さで、痛みはほとんど感じません。
お灸も心地よい温かさで、リラックス効果が期待できます。
施術時間は症状や体質によって異なりますが、30分~1時間程度が一般的です。
④アドバイス
施術後、施術者は日常生活における注意点や、自宅で行えるストレッチなどをアドバイスします。
施術の効果を持続させるためには、日常生活でのケアも重要です。
施術者からのアドバイスを参考に、再発防止に努めましょう。
足の裏の痺れを鍼灸以外で改善する方法
鍼灸治療以外にも、足の裏の痺れを改善する方法があります。
症状や原因によって適切な方法を選択することが重要です。
ここでは、代表的な改善策として、ストレッチ、マッサージ、投薬治療について解説します。
ストレッチ
足の裏の痺れには、ふくらはぎや太ももの裏、お尻の筋肉が硬くなっていることが関係している場合があります。
これらの筋肉をストレッチすることで、血行が促進され、神経への圧迫が軽減される可能性があります。
①ふくらはぎのストレッチ
壁に手をついて、片方の足を後ろに引きます。
かかとを床につけたまま、アキレス腱を伸ばすように体重を前にかけます。
この姿勢を20~30秒ほど維持し、左右の足を交互に行います。
②太ももの裏のストレッチ
床に座り、片方の足を伸ばし、もう片方の足を曲げます。
伸ばした足のつま先を両手で持ち、太ももの裏が伸びているのを感じながら、20~30秒ほど維持します。
左右の足を交互に行います。
③お尻のストレッチ
仰向けに寝て、片方の膝を曲げ、両手で抱えます。
胸の方に引き寄せ、お尻の筋肉が伸びているのを感じながら、20~30秒ほど維持します。
左右の足を交互に行います。
マッサージ
マッサージは、血行促進や筋肉の緊張緩和に効果が期待できます。
足の裏だけでなく、ふくらはぎや太もも、お尻など、関連する筋肉も一緒にマッサージすることで、より効果的です。
①足裏マッサージ
ゴルフボールやテニスボールなどを足の裏で転がし、刺激を与えます。
痛気持ちいい程度の強さで、数分間行います。
②ふくらはぎマッサージ
ふくらはぎを両手で包み込み、下から上に向かって、優しくもみほぐします。
③太ももマッサージ
太ももを両手で掴み、筋肉をほぐすように、優しくもみ上げます。
投薬治療
痺れの原因や症状によっては、医師の診断のもと、薬物療法が用いられる場合があります。
ここでは、代表的な薬の種類と効果について解説します。
| 薬の種類 | 効果 | 注意点 |
| ビタミンB12製剤 | 神経の修復を促進 | 医師の指示に従って服用 |
| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 炎症や痛みを抑える | 胃腸障害などの副作用に注意 |
| 抗うつ薬 | 神経障害性疼痛を緩和 | 医師の指示に従って服用 |
| 抗てんかん薬 | 神経障害性疼痛を緩和 | 医師の指示に従って服用 |
これらの薬は、必ず医師の診断と処方のもとで服用してください。
自己判断での服用は危険ですので、控えてください。
また、副作用が現れた場合は、すぐに医師に相談しましょう。
痺れの改善には、ストレッチやマッサージなどのセルフケアと並行して、適切な医療機関を受診し、専門家の指導を受けることが重要です。
自分の症状に合った方法を選び、継続的に取り組むことで、症状の改善を目指しましょう。
まとめ
足の裏の痺れは、放置すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
痺れの原因はヘルニアだけでなく、坐骨神経痛や末梢神経障害、糖尿病など様々です。
原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。
この記事では、足の裏の痺れの原因の一つとして、腰椎椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症などのヘルニアについて解説しました。
これらのヘルニアは、神経を圧迫することで足の裏に痺れを引き起こすことがあります。
また、ヘルニア以外にも様々な原因が考えられるため、自己判断せず、医療機関を受診して適切な診断を受けることが大切です。
鍼灸治療は、血行促進や神経機能の調整を通じて、足の裏の痺れを改善する効果が期待できます。
鍼灸治療以外にも、ストレッチやマッサージ、投薬治療など、様々な治療法があります。
ご自身の症状や体質に合った治療法を選択することが重要です。
痺れが続く場合は、我慢せずに専門家へ相談し、適切な治療を受けて快適な生活を取り戻しましょう。
何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
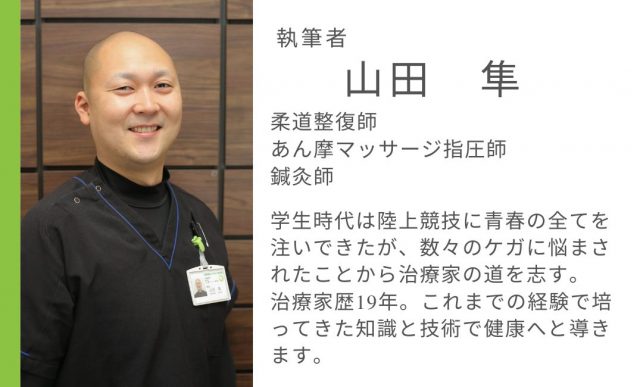

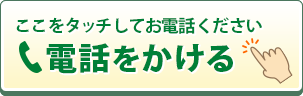
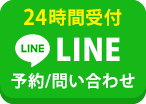
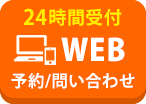





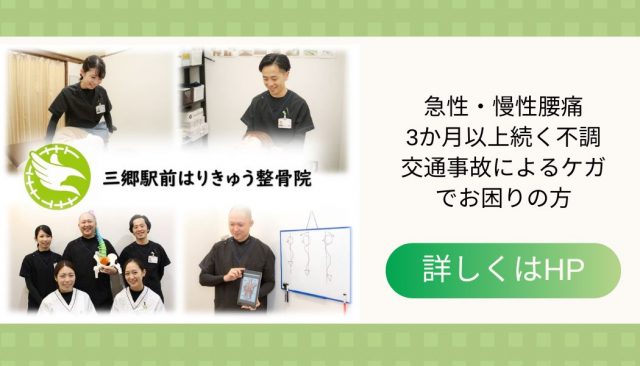
お電話ありがとうございます、
三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。